少し秋を感じたのも束の間、まだまだ暑い日々ですね。今日は安息日は“決まりではなく神様が与えてくださった恵み”と教えられました。(megu)
礼拝説教 中尾敬一牧師
おはようございます。今日もようこそお集まりくださいました。一週間の感謝をささげ、希望を確認し、主を恐れて、平安もって新しい週を踏み出す、この時を共に過ごさせていただける恵みを味わいましょう。
聖書を読んでいますと、私たちはどうしても「神の聖なる怒り」について向き合わざるをえません。そこには当然背景があり、どうして人が愛である神の怒りを受けることになってしまったのか、経緯が記されています。しかしながら、経緯が分かったとしても、「怒り」と聞いて、私たちがまず率直に感じるのは恐怖ではないでしょうか。神の怒りを前にして、私たちはどうしたら良いのでしょうか。
そのような私たちに聖書は、大胆に神の恵みを受けなさいと語っています。ヘブル人への手紙にはこう書いてあります。《罪と不法が赦されるところでは、もう罪のきよめのささげ物はいりません。こういうわけで、兄弟たち。私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのために、この新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには、神の家を治める、この偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて、邪悪な良心をきよめられ、からだをきよい水で洗われ、全き信仰をもって真心から神に近づこうではありませんか。(ヘブル10:18-22)》またIヨハネの手紙にはこう書いてあります。《子どもたち。私たちは、ことばや口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょう。そうすることによって、私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても、安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存じだからです。(Iヨハネ3:18-20)》
もし罪を行い続けているなら、神の怒りに恐怖するのは当たり前のことです。神である主の前に罪を悔い改めるべきです。しかし、罪を悔い改めて、いま御霊によって光の中を歩んでいるのなら、すべての罪は十字架の血潮によって精算され、赦され、またきよめられたのですから、大胆に聖所に入りましょう。たとえ自分の心が責めたとしても、主は救いの確信を与えてくださいます。
聖書をお開きください。アモス書8:4-8(1570ページ)【聖書朗読】
人と人の関係の歴史をたどると、夫婦関係から家族が生まれ、家族と家族の関係は隣人関係を築きました。主は愛を土台として、人の社会が建て上げられていくことを願っておられました。しかし人は主に逆らい、自分たちが神のようになって、自分の目に良いと思うことをし始めました。人は神である主を離れて、罪を治めることができなくなります。兄弟が争うようになり、親子が破綻し、主の御心に反して、主人と奴隷という関係が起こりました。家族や村から出ていった人は、城壁のある町を作りました。愛を土台とするのではなく、力と経済を土台にして社会が形成されていきました。愛があっても、お金がなければ生きていけないと言うようになったのです。
このような町の社会で、経済格差が起こり、格差はやがて固定され、階級ができるようになりました。そのような世界で、神の民は主の宝の民として選ばれ、主の律法を与えられました。もし主の掟を守るなら、民の間には貧しい人がいなくなるであろうと言われました(申15:4-5)。しかし、民は従順ではなかったので、貧しい人は絶えることがありませんでした。それで主は譲歩されて、貧しい人がいるという前提で、こう命じられました。《「あなたの地にいるあなたの同胞で、困窮している人と貧しい人には、必ずあなたの手を開かなければならない。」(申15:11)》貧しい人は支えられるべきであって、利用されるべきではないのです。
主は貧しい人を支えるための命令をいくつも与えられました。民からささげられた十分の一の捧げ物は、レビ人たちの生活のために与えられた他、貧しい人たちにも分けられました。収穫時の落ち穂は拾ってはならず、貧しい人たちのために置いておかなければなりませんでした。すべての人に与えられた土地は、たとえ他の人の手に渡ったとしても、一定期間の後に返されるべきでした。主のメッセージは明らかでした。貧しい人を利用してはならない。彼らを支えなければならない。なぜなら主は出エジプトの神であり、民をエジプトの奴隷から救ったお方だからです。民は主に倣って、生きなければなりません。
また主は、安息日を定められた時に、このように言われました。《安息日を守って、これを聖なるものとせよ。あなたの神、【主】が命じたとおりに。六日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。七日目は、あなたの神、【主】の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ろば、いかなる家畜も、また、あなたの町囲みの中にいる寄留者も。そうすれば、あなたの男奴隷や女奴隷が、あなたと同じように休むことができる。(申5:12-14)》安息日の起源は、天地創造の7日間にあります。安息日を守ることは、天地を造られた神である主を恐れることでした。そして7日目は、マナを集めなくても食べることが出来た日、神の恵みによって生きていることを味わう日でした。安息日には働いてはならない、そして、「働かせてはならない」のです。これもまた、貧しい人たちを守り、支える掟でした。
ところが、民のうち、特に奴隷を多く働かせていた人たちは何を言っていたのでしょうか。5-6節《「新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが。安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが。エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの秤で欺こう。弱い者を金で買い、貧しい者を履き物一足分で買おう。屑麦を売ろう。」》彼らの頭の中は利益を上げることでいっぱいでした。主を恐れる気持ちは少しもありません。利益のためなら、不正な測りを使っても構わないし、弱く、貧しい人たちをいくら働かせても構わないのです。聖なる主は、このことに怒りを現されました。
私たちクリスチャンは、金曜日日没から土曜日日没の安息日にではなく、イエス様がよみがえられた希望と勝利の日曜日に安息をおぼえています。日曜日ごとに集まって礼拝しています。この毎週の日曜礼拝について、私たちはどのように考えているでしょうか。_ 「教会は日曜日に働いている人たちに優しくない」という意見があります。「サービス業界は日曜日に休むのはほとんど不可能だ。その業界にいる人たちに、日曜礼拝を選ばない人とレッテルを貼り、冷たく接している。伝道だって日曜日に誘うのは難しい。」心に留めておくべき大切な意見だなと思いました。色々なことを思い巡らしました。しかし同時に、こうも思いました。安息日の本来の意図は、過酷な労働を課す主人から弱く貧しい人たちを守り、働かなくても良いようにすることでもあったのです。日曜礼拝が優しくないという方向に進んでいけば、自分の首を締めることになってしまうのではないでしょうか。
大学生の頃、とんかつ屋でアルバイトをしていました。仕事の日がシフトで決まるわけです。ある時、夏休み中だったと思いますが、一緒に働いていた友人が言うんです。「俺、もう20連勤だわ~。やばい。」大学生ですから「すげぇな」なんて言っていたわけです。でも、大人になってよく考えてみたら、「安い賃金で沢山働かされてたってことだよね。会社はウハウハだっただろうけれど、すげぇことではなかったな」と思いました。自分の労働の価値を十分に知らない大学生や、外国人たちが安く買い叩かれているわけです。昨今もビジネス業界では人手不足だと言われているそうですが、よく実態を見てみると、企業が求める安い賃金で働いてくれる人が少なくて、そういう人々を確保するために争奪戦になっているとか。
貧しい人は支えられるべきであって、利用されるべきではないと、主は教えられました。書き入れ時である日曜日にレストランを閉めるクリスチャンオーナーがいます。教会が圧をかけて仕事を妨害しているのでしょうか。日曜日は働いてはいけないとルールを決めて、ただでさえ厳しい飲食業界の人々を苦しめているのでしょうか。いいえ、主は安息の日に、貧しい人を守り、支え、救い、養おうとしておられます。だから、安心して休めるのです。オーナーも従業員も、働かされることから守られ、一緒に休むことができます。
主イエス様は安息日に人を癒やされました。パリサイ人たちはイエス様を非難し、律法に違反していると言いました。しかし、安息日の律法が本来何を意図していたかを考えれば、イエス様が正しいことは明白です。安息日は主人の酷使から奴隷が守られる日でした。奴隷の主人たちは、彼らを休みなく働かせて利益を1円でも多くすることばかり考えていたからです。しかし、イエス様は安息日に人を癒やし、病から救われましたが、自分の利益のためにそうされたのではありませんでした。イエス様は癒やされた人に、このことを誰にも言ってはならないと言われました。人々がご自分を王として連れて行こうとした時にも、その場を去っていかれました。利益のために誰かを働かせることはありませんでした。
働き詰めの人々に、私たちは沢山のことを良い知らせとして伝えることができます。多くの人は働き続けないと収入が減って生きていけなくなるのではないか、ボスに嫌がられて仕事を失ってしまうのではないかと心配しているのではないでしょうか。主が私たちの生活を恵みによって支えてくださるということ。利益のために人々を働かせ続けることを許さないで、貧しい人々を守ってくださること。そのような良い知らせを、生まれてから一度も聞いたことがない人がいるのです。働かなくても大丈夫と言われたことがない人がいます。「主は生きておられて、あなたを支え、守ってくださる。だから主にゆだねて、安心して休もう」と伝えるなら、これは伝道ではありませんか。
あるいは、働き続けることが好きでやっているんだという人がいたなら、自分が働くことで、他の人たちを働かせ続けていることに気が付いていないかもしれません。主は人の心を見て、正しく裁かれるお方です。主を恐れようと伝えることができます。
もし安息日の意図をよく理解しないで、日曜礼拝に来るか来ないかという表面でしか見ていないなら、パリサイ人の失敗を繰り返すことになります。そういう状況であれば「教会は日曜日に働いている人たちに優しくない」という人がいるのも頷けます。《七日目は、あなたの神、【主】の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ろば、いかなる家畜も、また、あなたの町囲みの中にいる寄留者も。そうすれば、あなたの男奴隷や女奴隷が、あなたと同じように休むことができる。(申5:14)》安息日の意図は、人を酷使してはならないということです。貧しい人を利用するのではなく、支えなければならないと主は言われます。
お祈りします《【主】はヤコブの誇りにかけて誓われる。「わたしは、彼らのしていることをみな、いつまでも決して忘れない。》
天の父なる神様。神の神、主の主、偉大で力があり、恐ろしい神。えこひいきをせず、賄賂を取らず、みなしごや、やもめのためにさばきを行い、寄留者を愛して、これに食物と衣服を与えられるお方。私たちの主よ。
あなたは貧しい人がいることを良しとされません。しかし、この世は貧しい人たちを働かせることを当たり前のことにしています。それが嫌なら努力して上にあがれと言うのです。貧しい人たちの叫びは天に届いているのではないでしょうか。あなたの裁きはもう間近に来ています。主よ、あわれんでください。
私たちは福音を携えています。主の安息を知らせることができます。どうぞこの一週間も、私たち一人ひとりを福音を宣べ伝えるものとして用いてください。
主イエス様のみ名によってお祈りいたします。アーメン。
![インマヌエル王寺キリスト教会[奈良県王寺町の教会]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpLQYEAtJ_uTBAe-KrJXjYYCIGsg0DZZgLlXZEed8SwMD5EoutkbLV7HQnNAPHceSLxKdJhO6npwzgl7R__tXPEKeiOd-oCmoPOkBKP0sjug9TR1UjhuomyCicvUQFdKiACuFVmb1q8sE/s1600/%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AB.png)



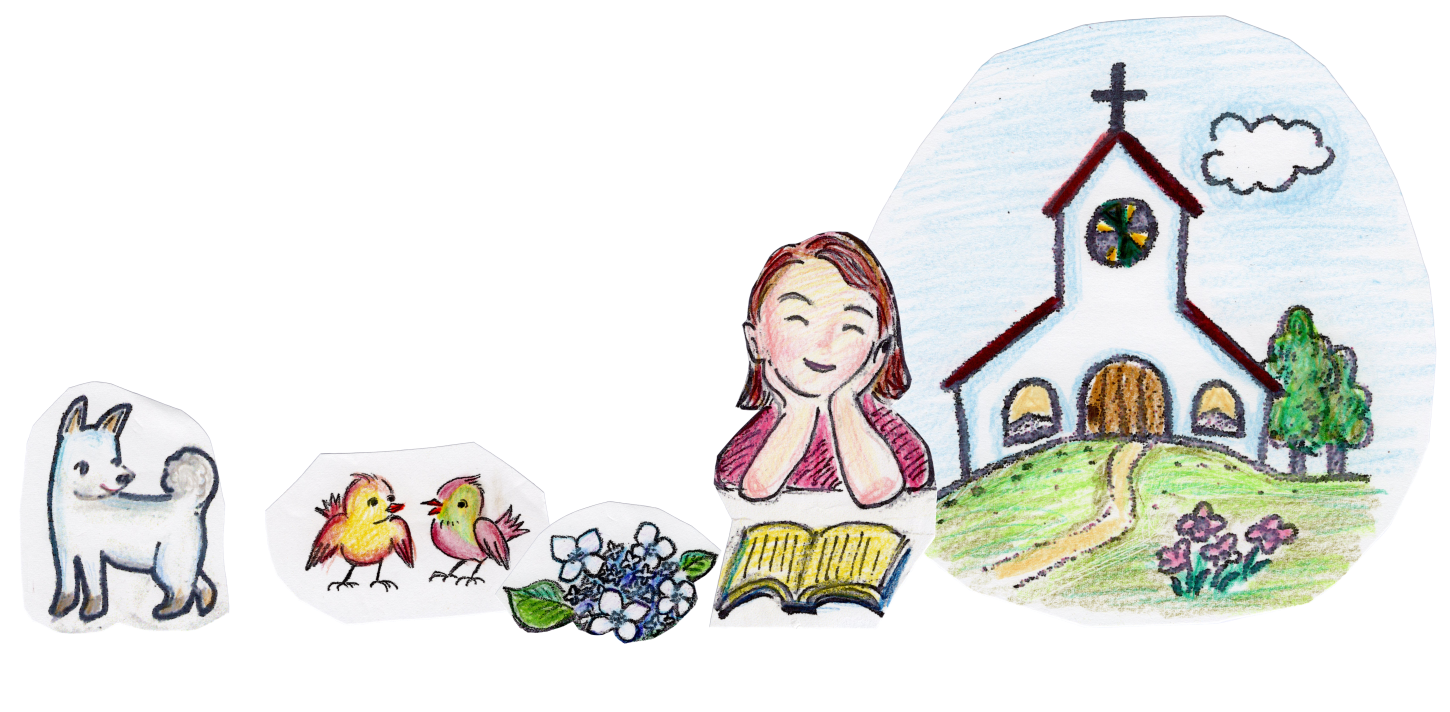
0 件のコメント:
コメントを投稿