私たちが直面する試練は信仰を引き上げられるために主から与えられるもの。試練には学ぶべきことがあると教えられました。試練に負けそうになる時もありますが、主が共におられることを忘れずに乗り越えていきたいです。(megu)
礼拝説教 中尾敬一
おはようございます。今日もようこそお集まりくださいました。私たちは神である主の御前に呼ばれ、集められた者たちです。ギリシャ語でエクレシアと言います。自分で行こうと思って来たのに、実は神によって集められたというのです。不思議なことです。
昨日は奈宣協の講演会が開かれ、クリスチャンとして中東問題を知るというテーマでお話を聞きました。超教派の集会でしか聞くことがないだろうなと思うお話を興味深く聞かせていただきました。主がどんなに神の民イスラエルを愛してこられたか、そしてそれが歴史的事実であって、現実にユダヤ民族が存在することの意味を、再臨の希望に見ながら、思いを巡らせる時となりました。その中で私が思いましたことは、私たち異邦人クリスチャンも(かつては神の民ではなかったのに)神の民とされたとは、どれほどの特権かということです。実に後の者たちが長子の権利をいただいたのです。聖書はこのことをこう表現しています。《枝の中のいくつかが折られ、野生のオリーブであるあなたがその枝の間に接ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分をともに受けている(ローマ11:17)》イエス様を信じなかったユダヤ人が神の民という木から折られてしまったということ、その代わりにイエス様を信じた異邦人が接ぎ木され、イエス様を信じたユダヤ人(折られなかった枝)と共に神の民として、あたかもアブラハムの子孫であるかのようにみなされ、栄養を受けているということです。しかし、こうも書いてあります。《あの人たちも、もし不信仰の中に居続けないなら、接ぎ木されます。神は、彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。(ローマ11:23)》主の愛は決して見捨てることない愛です。折られたら終わりだと思うのが人間の考えです。しかし折られたのは再び接ぎ木されるためでした。(もちろん「不信仰の中に居続けないなら」ですけれども)そのような特別な愛を与えられてきた神の民に、こんな私たちもあわれみによって加えられたのだということは、なんと驚くべきことでしょうか。ユダヤ人も異邦人も、すべての人たちがイエス様を信じるように、とりなして祈りましょう。
聖書をお開きください。マタイの福音書14:22-33(29ページ)【聖書朗読】
先月はイエス様が5,000人以上の人々に食事をお与えになられた箇所を開きました。今日はその続きの出来事になります。またガリラヤ湖での出来事なのですが、実はイエス様の教えと奇跡はほとんどガリラヤ湖の周辺で行われました。一度だけ更に北のツロやシドンに行かれ、その他には首都エルサレムに何度か、エルサレムとガリラヤ地方の途中にあるサマリヤも通られたことがありました。しかし、ほとんどガリラヤ湖周辺で、公生涯の数年を過ごされました。それはイエス様がガリラヤ地方のナザレという町で育たれたからです。
ガリラヤ地方というのは、ヘロデ王の領土の中でサマリヤよりも北にある、一番端の辺鄙な地域でした。奈良県で言えば吉野郡のような端っこの地域です。イエス様はエルサレムの横にあるベツレヘムの馬小屋でお生まれになったのですが、ヨセフとマリヤはヘロデ王の乳幼児(2歳以下)大虐殺から逃げて、エジプトでしばらく過ごした後、ガリラヤ地方の町ナザレに行って住んだのです(マタイ2:19-23)。どうやらナザレの近くに新しい都市建設が行われていて、大工のヨセフが仕事をするのにちょうど良かったようです。
ガリラヤ地方には大きな湖がありました。南北に21Km、東西に13Kmで、だいたい琵琶湖の四分の一くらいですが、それでも向こう岸は水平線に隠れて見えないくらい大きい湖です。湖の周りには、カペナウム、ベツサイダ、マグダラ、ゲネサレ、ティベリアなどの町がありました。ガリラヤ湖、ゲネサレ湖、ティベリア湖といくつか呼び方がありますが、福音書に出てくる湖は全部ガリラヤ湖のことです。
さて、イエス様一行と群衆は追いかけっこをするように、ガリラヤ湖周辺を移動していました。イエス様の弟子にはペテロやアンデレなどの漁師がいましたので、陸地を移動する以外にも、湖を舟で渡ることができました。福音書をよく読むと、イエス様専用の小舟が一艘あって、時々、弟子たちの舟とは別行動で湖をお一人で渡っておられたことがわかります(マタイ14:13、22、ヨハネ6:22)。「水の上を歩けるのなら、舟なんか使わないでいつでも歩いていったら楽じゃないの」と思うのですが、イエス様が奇跡を行われるのは明確に目的がある時だけでした。イエス様は弟子たちに何を教えてくださろうとしたのでしょうか。
今回のイエス様の奇跡は、ガリラヤ湖の嵐を鎮めるという御業でした。ところで、みなさん、湖の嵐で弟子たちが死にそうになって、イエス様に助けを求めたら助かったという場面を他にもご存じないでしょうか。実はマタイの福音書8:23-27にも似たような出来事がありました。《それからイエスが舟に乗られると、弟子たちも従った。すると見よ。湖は大荒れとなり、舟は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、「主よ、助けてください。私たちは死んでしまいます」と言った。イエスは言われた。「どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。」それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。すると、すっかり凪になった。人々は驚いて言った。「風や湖までが言うことを聞くとは、いったいこの方はどういう方なのだろうか。」》ですから、今回は初めてではありませんでした。でも、違いがあります。前回はイエス様が同じ舟に乗っていて、眠っていました。今回は、イエス様が舟に乗っていませんでした。イエス様が眠っておられたので怖がってしまった弟子たちです。今度は、イエス様が乗っていない舟で、夕方から夜明けにかけて、電気もない真っ暗な湖の真ん中で、どのように過ごしたのでしょうか。どんなにか怖い思いをしたことでしょう。確かに客観的に見れば、イエス様は段階的に彼らの信仰を引き上げようと、レベル1からレベル2の試練を備えられたのです。しかし、それに直面する弟子たちにとっては、「前はイエス様によって救われたけれど、今度はもっと大変な状況になった、果たして今回は…」という場面でした。神である主が救われる時、不可能なことはないのです。小さなことで救われたなら、大きなことでも恐れることはありません。
波に悩まされ続け、怖がっていた弟子たちに、イエス様はご自分の姿を表そうと思われました。マルコの福音書によると、イエス様はそばを通り過ぎるおつもりだったようです(マルコ6:48)。イエス様は、弟子たちがイエス様の姿を間近に見れば、それで安心するだろうと期待しておられました。ところが、「幽霊だ!」と言って怯え、恐ろしさのあまりに叫んだのでした。
そもそも、旧約聖書の時代から現在に至るまで、神である主は目に見えないお方です。目に見えないお方がいつも共にいてくださって、私たちが助けを叫ぶ時に救ってくださることを人々は経験してきたのです。確かに御子イエス様は人の罪を背負うために、受肉し、完全な人として生まれてきてくださったので、その副次的な効果として、歴史上で30数年の間だけ、人間が神様の姿を自分の目で見て、じっと見つめ、手で触ることができたのです(Iヨハネ1:1)。すると、イエス様が舟に乗っておられるときは、主が共におられるように感じ、イエス様が舟に乗っておられないときには、共におられないように感じました。目に見えないお方のほうが、共におられることを信じられるのかもしれません。人間の感覚とは実に不確かなものです。
彼らはイエス様を見たとき、主が共におられたと分からずに、自分たちの理解の範囲で目の前の出来事を捉えました。幽霊というのは、現代人はあるとは思えない現象かもしれませんが、当時の彼らには「幽霊という可能性は有り得る」と思えたのでした。私たちに置き換えるなら、イエス様がそこにおられると分かるよりも、「精神的に参ってしまったのかな」とか、「湖の動物の影かな」とか、「プロジェクターで立体映像を映し出しているのかな」とか考えたということです。冷静に考えたら、そんなことだって起こりそうもない事柄ですが、主が共におられるとは気が付くよりも、変な現象が起こって不気味だと怖がってしまうことの方がありがちではないでしょうか。
しかし、そんな弟子たちに、また私たちに、主イエス様は《「しっかりしなさい。わたしだ。恐れることはない」》と言われました。「わたしだ。」この言葉は、主ヤハウェのお名前「わたしはある」を力強く思い出させます。どんなに激しい嵐の中でも、動かされず、水の上に立つお方として、私たちのそばに共にいてくださるのがイエス様です。このイエス様について、あなたはどう思われますか。人生の大嵐に遭遇して、「私がこんな目に遭うなんて神も仏もあるか」と思える時に、主は「しっかりしなさい。わたしだ。」「わたしはある」と語りかけ、ご自身を現してくださいます。
人は追い詰められた時に主を見ると、イエス・キリストだとは思わないで、変な現象が起きたに違いないと思うようです。「だって嵐が起こる前は、舟にイエス・キリストは居なかったのだから。」イエス様はそばを通り過ぎるだけで良いだろうと、主が共におられることを思い出して安心するだろうと思われたかもしれませんが、弟子たちはそれでは駄目でした。
ペテロは言いました。《「主よ。あなたでしたら、私に命じて、水の上を歩いてあなたのところに行かせてください」》ちょっと急に意味がわからないことを言っています。でも、思い出してください。真っ暗な夜中ずっとコントロールを失った舟の上で波に揺さぶられ、死を恐れ、疲労困憊していました。明るい昼間に、陸地で、落ち着いてイエス様の姿を見れば、簡単に分かったでしょう。だけどこんなに切羽詰まったときにはどうでしょうか。彼なりに主が共におられることを確かめたいと思ったのです。ペテロはすぐにこういうことをする性格だったみたいですが、私たちも彼のようにやってみたら良いと思います。昨年クリスマスコンサートに来てくださったよつ葉教会の東先生も、「主よ、あなたが本当におられるなら、流れ星をみせてください」と祈ったそうです。そして主は3度も異なる角度から流れ星を見せてくださったと証しておられました。
イエス様が舟に乗り込まれると、途端に嵐はやみました。嵐に遭ったら大変だと慌て、嵐がやんだら良かったといって済ませてしまうことがあります。しかし、すべての試練には学ぶべきことがあります。舟に主が乗っておられなくても、主はいつもあなたと共におられるということです。「わたしだ」「わたしはある」と力強く語りかけてくださいます。
主が臨在(存在を暗示するしるし)を見せてくださるとき、幽霊だろうと決めつけるべきではありません。本当にあのイエス・キリストなのか!?と思ったなら、確かめてみましょう。イエス様は「来なさい」と答えてくださいます。
お祈りします《イエスはすぐに彼らに話しかけ、「しっかりしなさい。わたしだ。恐れることはない」と言われた。》
天の父なる神様。私たちの神、主よ。まことにあなたは私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられます。
私たちは自分の周りの世界が、自分の知っている現象で成り立っていると思いこんでいます。イエス様が同じ舟に乗っておられるなら、眠っていても、叩き起こせば何とかなると思い、もし同じ舟に乗っていないなら、共におられないのだから、どうしようもないと考えます。主が共におられることを現してくださっても、舟におられないのだから、気が迷ったに違いないとか、何かの影を見たのだろうとか、別の音を聞き間違えたとか、そのように考える傾向があります。このような私たちをあわれんでください。
舟に乗っておられなくても、あなたはいつも共にいてくださることを教えてください。私たちと共におられる主よ。今朝も、私たちはあなたを礼拝します。
主イエス様のみ名によってお祈りいたします。アーメン。
![インマヌエル王寺キリスト教会[奈良県王寺町の教会]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpLQYEAtJ_uTBAe-KrJXjYYCIGsg0DZZgLlXZEed8SwMD5EoutkbLV7HQnNAPHceSLxKdJhO6npwzgl7R__tXPEKeiOd-oCmoPOkBKP0sjug9TR1UjhuomyCicvUQFdKiACuFVmb1q8sE/s1600/%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AB.png)



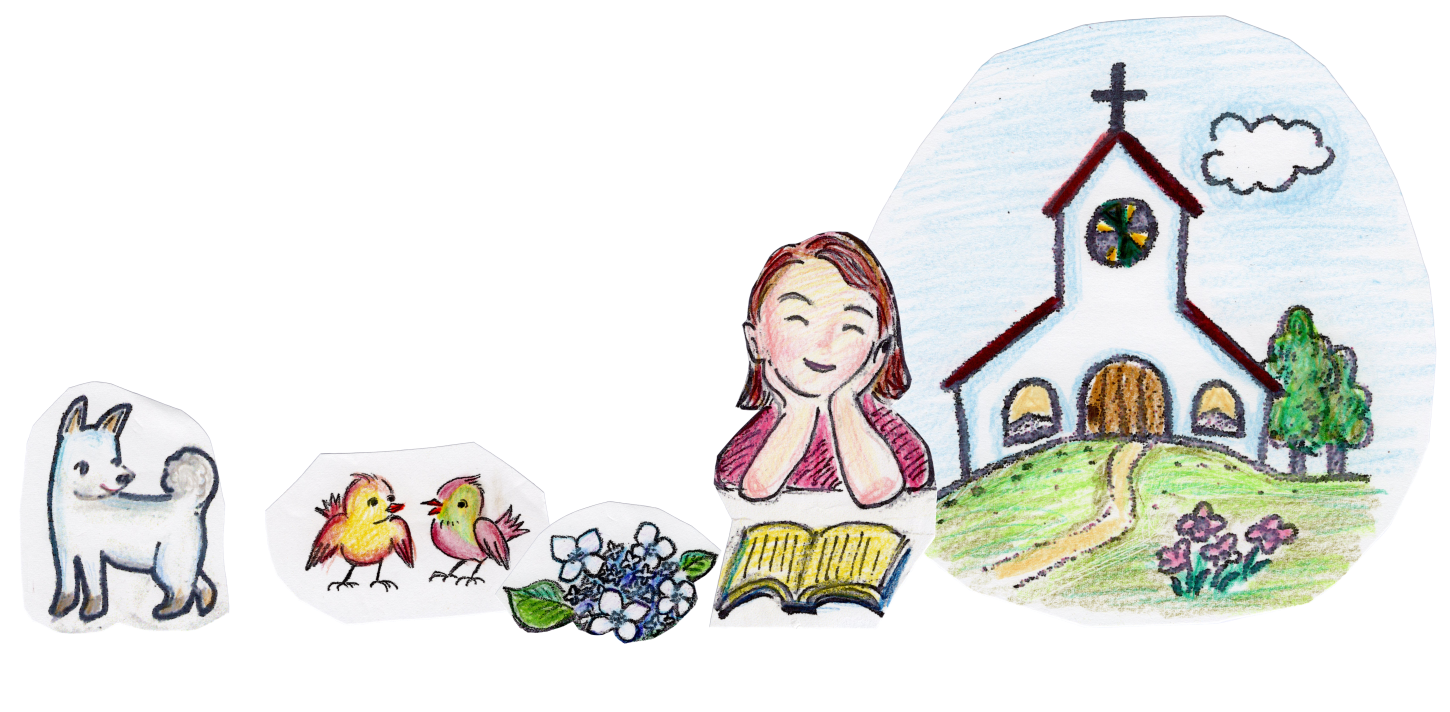
0 件のコメント:
コメントを投稿