おはようございます。上半期の最後の週を迎えています。この半年はどのような出来事があったでしょうか。このように振り返る時、私たちは、それぞれの人生に現れてくださった主を思い出すようにしましょう。
私たちが住む世界では、一般的に、あるグループが上半期を振り返って総括するといえば、どんな行事をしたか、行事に何人集まったか、どんな重要人物が来たか、目標は達成できたか、どんな工夫をしたか、メンバーとのコミュニケーションはどうだったか、やる気は上昇したか、活気があったかなど、そのようなことを思い出して話し合うことでしょう。しかし、イエス様の教会ではそのような振り返り方はしません。そうやって振り返っても、バベルの塔を造るかもしれませんが、神の国を建てあげることがないからです。また、そのような話し合いの中には主イエス様の居場所がありません。話し始める前と一通り話し終わった後に、とりあえずお祈りをして、「神様ありがとうございました」とお決まりのフレーズを唱えるかもしれませんが、話の真ん中にイエス様がいないということは、本当に悲しいことです。「イエス様~。これから振り返り会をしますので、最初のご挨拶お願いします。」「はい。それじゃ、ちょっと話し合いますので、あちらの控室の方でお待ち下さい。一応こちらの声は聞こえるようになってます。」「イエス様~、終わりました。最後の締めますから来てください。代表からの感謝の言葉を聞いて下さい。」こんな感じでしょうか。しかし、私たちの人生に現れてくださった主の話をするなら、イエス様を囲んで、「あの時はこうしてくださいましたね。」「この時は…」と話すことができます。
聖書がどのように過去を振り返っているか、よく注目して読んでみていただきたいと思います。直接、主が登場しなくても(ルツ記、エステル記など)、主が人々の歩みに介入して、御業をなされたことが明らかになっています。私たちがどんな活動をしたか(何を起こしたか)よりも、私たちの人生に何が起こって、主が何をしてくださったかの方が重要です。主は私たちの人生の出来事に介入して、御業をなされます。
イエス様がよみがえられた後、弟子たちの会話はこうでした。「私は主を見ました(ヨハネ20:18)」「私たちは主を見た(ヨハネ20:25)」現代でもクリスチャンの会話は変わりません。週に一度、顔を合わせる度に、私たちは主を見たと互いに証しあって、励まされています。この半年、主はいつどのようにあなたの人生に、また私たち王寺教会の歩みに現れてくださったでしょうか。自分だけの秘密にしておかないで、分かち合い、共に感謝しましょう。
聖書をお開きください。申命記15:12-18(343ページ)【聖書朗読】
主人と奴隷(しもべ、家来:エベッド)の関係を聖書から学んでいます。
今日の箇所は出だしから、戸惑ってしまうと思います。前回、開いたレビ記25章では、こう書いてありました。《もし、あなたのもとにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身売りしても、彼を奴隷として仕えさせてはならない。彼はあなたのもとでは雇い人か居留者のようでなければならず、ヨベルの年まであなたのもとで仕える。…彼らは、わたしがエジプトの地から導き出した、わたしのしもべである。奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を酷使してはならない。あなたの神を恐れよ。(レビ25:39-43)》神の民の間では、隣人を奴隷にしてはならないとハッキリ教えられていたのに、今日の箇所を読むと、すでにヘブル人の奴隷がいるという前提で話が始まっているのです。
聖書をじっくり詳しく調べて読むと、他にもこのような箇所が見つかります。でも、「なんだ矛盾しているじゃないか」と安易に考えないでください。これは民のうなじが固かったこと、また主が忍耐のお方であることを証明しているのです。うなじとは首の後ろの部分です。ここが固いと、「はい」と頷くことができません。神の民は口先では「主に聞き従います(出24:7)」と言ってきましたが、行動で反抗しました。しかし、主は忍耐をもって、それならばこう、それならばこう、と彼らの現状に合わせて神の国の義を教えてくださってきたのです。実は現代の教会でも同じことが起こります。「聖書ではこのように語られています。教会はこのよう考えます。教会はこういう生き方をします。イエス様の教えはこうです」と語られるのを聞いた後で、それと違う姿を見聞きすることが、まれに、良くあるのです。真面目に主のことばに従おうとしている人が茶化されたりする時さえ有り得ます。しかし、人に冷水をかけられても、主の前に誠実に生きる人は幸いです。主がその行いに報いてくださいます。
かつての神の民のように「うなじの固い」姿は、主を恐れていないと言います。非常に平たく言えば、「神である主をなめてる」ということです。主を恐れるとは、御言葉から語られたことを重要だと受け止めて、聞き従うことです。主が忍耐(譲歩)してくださるのは、主がご自分の民を愛しておられるからです。しかし、愛しあっている夫婦であっても、例えば夫が妻をなめているなら、忍耐の限りがあるでしょう。ご主人は「家内が突然怒った。寝耳に水だ」と驚くかもしれませんが、突然ではないですよね。目盛りが1、2、3と上がっていて、限界ラインまでスムーズに到達したわけです。イスラエル王国はある日突然、国を滅ぼされてしまったのですが、それは主の目から見れば、突然だったのではないということです。
さて、話を戻しまして。ヘブル人の奴隷がいる前提であれば、どうなのでしょうか。出エジプト記にも同じ教えがありますので、こちらも読んでみましょう。出エジプト記21:2-6《あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は六年間仕えなければならない。しかし七年目には自由の身として無償で去ることができる。彼が独身で来たのなら独身で去る。彼に妻があれば、その妻は彼とともに去る。彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、この妻とその子どもたちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならない。しかし、もしもその奴隷が『私は、ご主人様と、私の妻と子どもたちとを愛しています。自由の身となって去りたくありません』と明言するようなことがあるなら、その主人は彼を神のもとに連れて行く。それから戸または門柱のところに連れて行き、きりで彼の耳を刺し通す。彼はいつまでも主人に仕えることができる。》
ヘブル人の奴隷は、まず期限付きだということです。7年目には自由の身にしなければなりません。またヨベルの年と呼ばれる、借金が帳消しになる年がありますが、その年にも奴隷を自由の身にしなければなりません。さらに無償で去らせなければならず、自由になるためのお金を要求することはできません。そして、それだけではなく、自由の身として去らせるときには、羊の群れと打ち場と踏み場を分けてあげるのです。そうすれば、自由になった人は、再出発し、これから自分で生計を立てていくことができるようになります。これは私たちが世で馴染んでいる、雇用とは全く様子が違います。神の民は、このように同胞をしもべとすることで、困窮している、貧しい同胞を助けるのです。
現代には、多くの人が事業をしています。事業が大きくなってくると、ひとりでは回らなくなってくるので、会社を作り、人を雇います。人々がどうして事業を始めようと思ったのか、インタビューした調査がありました。その理由の上位5つは次のようなものでした。1.お金持ちになりたいと思った。サラリーマンよりも、成功した時の報酬が多いから。2.尊敬できる起業家と出会った。ある人が成功している姿を見て、私も成功したいと思った。3.ビジネスアイデアが浮かんだ。競合があまりいない、ビジネスチャンスを見つけたから。4.今の仕事に不満があった。人に雇われてではやりたい仕事ができないから。5.会社が倒産した。急な失業で転職先が見つからなかったから。このような回答でした。ここには「困窮する人に収入を与えたいと思った」という理由は入っていません。自分の収入を何とかすること、夢を叶えること、人生を成功させることを目的として、事業を始め、自分の事業を助けてもらうために、労働力を買うのです。
しかし、神の民の間の主人と奴隷の関係はそのようではありません。父の家では、まず家族が共に働いているのですが、そこに売られてきた奴隷も加わって、家族のように共に仕事をします。奴隷が買われるのは、仕事の手伝いが必要だからではありません。同胞が困窮し、貧しくなったのをみたからです。主人はしもべが生活できるように、食事と住むところを提供します。また奴隷が独身だったときには、妻を与えることもありました。もちろん無理やり結婚しろということではありません。そのようにして家族の一員のようにお世話をするということです。やがて何年かして、自由の身になれる日が来たとき、しもべが「主人と主人の家族を愛し、主人のもとにいて幸せなので、去りたくないと言う」ことも起こり得る、愛の関係が築かれます。
この律法を読んで、どう思われますか。「それって、もはや奴隷ではないよね」と思いませんか。そうです。神の民の間に奴隷がいる前提で話し始められたのに、内容を読んでみると、奴隷と呼ばれていても、実体は私たちが想像する奴隷ではないと分かるのです。そこで主のことばを思い出します。《もし、あなたのもとにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身売りしても、彼を奴隷として仕えさせてはならない。(レビ25:39)》結局、主がおっしゃりたいのはこのことです。
「このような律法に生きていたイスラエル人たちの社会は、どんなに素晴らしかったのだろう。どんな社会になったのか知りたいな」と思われたでしょうか。しかし、残念ながら、うなじの固い民は主のおきてに従わなかったようです。エレミヤ書34章に、こんな出来事が記録されています。《ゼデキヤ王がエルサレムにいる民全体と契約を結んで、彼らに奴隷の解放を宣言した後、【主】からエレミヤにあったことば。その契約は、各自が、ヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身にし、同胞のユダヤ人を奴隷にしないというものであった。契約に加わったすべての首長と民は、各自、自分の奴隷や女奴隷を自由の身にして、二度と彼らを奴隷にしないことに同意し、同意してから奴隷を去らせた。しかしその後で、彼らは心を翻した。そして、いったん自由の身にした奴隷や女奴隷を連れ戻し、強制的に彼らを奴隷や女奴隷の身分に服させた。(エレミヤ34:8-11)》これに続いて、主のことばが預言者エレミヤを通して語られましたが、ついに神の怒りがくだると宣言されてしまいました。
神を知ろうとしない世の有様と、神の国の義は、根本的に異なっています。自分の収入を増やすために、自分の夢を叶えさせるために、自分の人生を成功に導くために労働力を買おうとする世界で、神の国の義に生きる人々は、落ちぶれて困窮し、貧しくなった隣人を助けようとします。そのように神の国の義に生きるなら、私たちは生き方によって福音を宣べ伝える者となります。人々は不思議がって、「なぜあなたは他の誰もしていないような生き方をしているのですか」と聞いてくるでしょう。その時、「私は聖書から神の国の生き方を教わりました。これは主イエス様の教えです」と答えられます。それをきっかけに主が生きておられること、人は主を知らず、主に逆らって生きていること、イエス様の十字架による赦し、そして神の国に招かれていることを伝えることができるでしょう。
お祈りします《その人を自由の身として去らせるときは、何も持たせずに去らせてはならない。必ず、あなたの羊の群れと打ち場と踏み場のうちから取って、彼に分けてやらなければならない。あなたの神、【主】があなたに祝福として与えられたものを与えなければならない。》
天の父なる神様。民がエジプトの地で奴隷であったとき、彼らを贖い出してくださった主よ。
かつて神の民が約束の地を与えられたのは、彼らが正しかったからではありません。うなじの固い民が荒野でどれだけあなたを怒らせたのか、忘れずに覚えていなければなりません。どうか主が私たちのただ中にいて、進んでくださいますように。確かに、あなたの民はうなじを固くする民ですが、どうか私たちの咎と罪を赦し、私たちをご自分の所有としてください。
私たちが心配している私たちの収入や生活の必要はあなたが満たしてくださいます。神の国とその義を求めるなら、主であるあなたがあふれるほどに与えてくださいます。また人生はあなたが成功させてくださいます。あなたが共にいてくださるなら、ヨセフのように、私たちのすることすべてをあなたが成功させてくださいます。心配事も自分の夢も、一切を御手の中に委ねて、イエス様に従います。仕えられるためではなく、仕えるために来てくださった主よ。あなたの後を従わせてください。
主イエス様のみ名によってお祈りいたします。アーメン。
![インマヌエル王寺キリスト教会[奈良県王寺町の教会]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpLQYEAtJ_uTBAe-KrJXjYYCIGsg0DZZgLlXZEed8SwMD5EoutkbLV7HQnNAPHceSLxKdJhO6npwzgl7R__tXPEKeiOd-oCmoPOkBKP0sjug9TR1UjhuomyCicvUQFdKiACuFVmb1q8sE/s1600/%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AB.png)




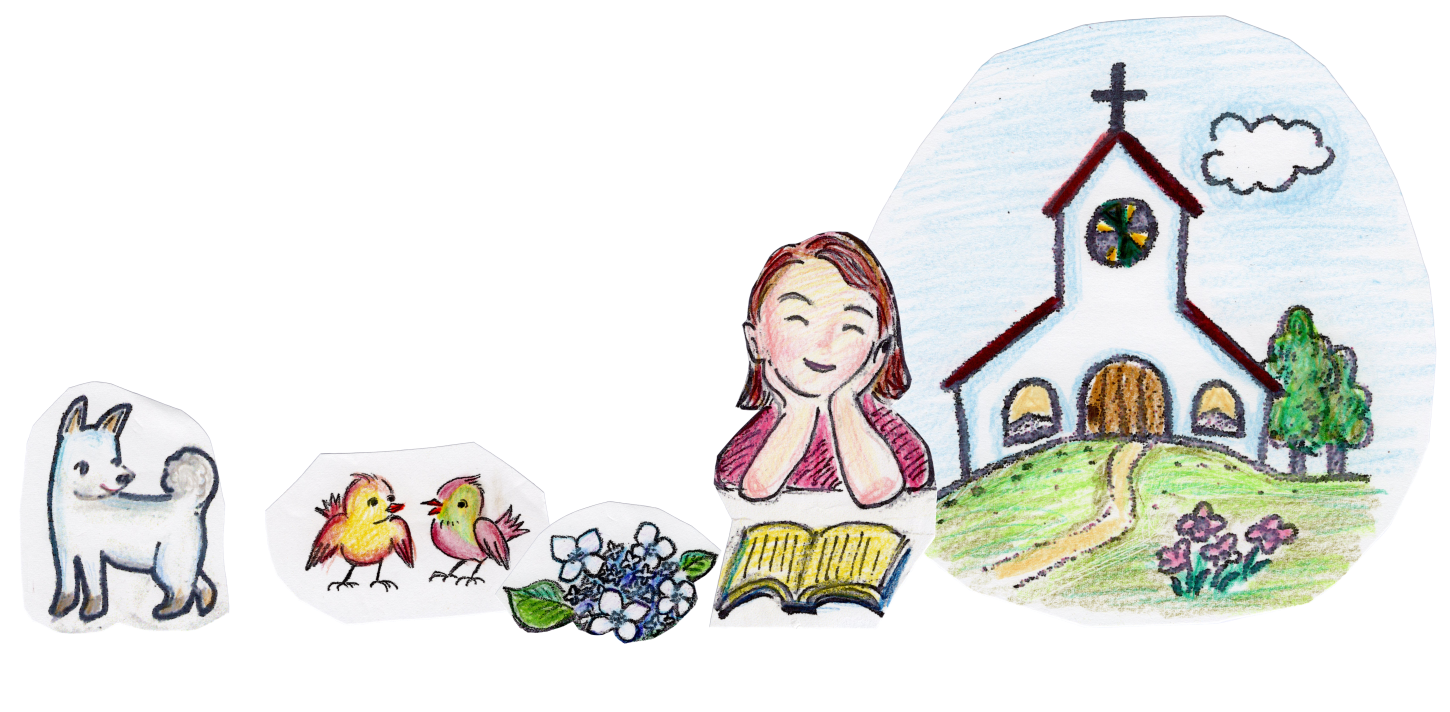
0 件のコメント:
コメントを投稿