自分の正義感には愛や恵みが含まれていなかったと気付かされました。「それにも関わらず」愛してくださる神様と共に、愛と恵みを携えて今週も過ごしていきたいと思います。(megu)
中尾敬一牧師
おはようございます。宣教月間の2週目に入っています。先聖日は、説教の冒頭で、教会は神の宣教であり、神の宣教は教会であるという話をいたしました。私たちがここに座って礼拝をしていても、それは山の上にある町です。私たちはまず主イエス様に救われた人たちとして存在していることで、主を宣べ伝えています。それでは、クリスチャンが外に出ていって宣教することは、どのように考えたら良いのでしょうか。私たちは座っているだけではありません。全世界にまで出ていって、主が死んで3日目によみがえられたこと、悔い改める者の罪が贖われること、主が私たちを迎えに帰ってこられることをあらゆる人に伝えています。
イエス様が十字架にかけられる数日前のことです。イエス様がロバに乗って、これからエルサレムに入場されようとしていた時、大勢の弟子たちが、自分たちが見たすべての力あるわざについて、喜びのあまりに大声で神を讃美し始めました。パリサイ人がそれを見て、イエス様に向かって「弟子たちを叱ってください」と言いました。するとイエス様は答えられました。《「わたしは、あなたがたに言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。」(ルカ19:40)》
神の宣教には、お決まりの流れがあります。イエス様はよみがえられた後、弟子たちに「あなた達はあらゆる国の人々に福音を伝える証人となります」と言われましたが、まずは都に留まっていなさいと言われました。それで弟子たちは都に留まって祈っていたのです。すると聖霊が彼らの上にくだりました。戸に鍵をかけて隠れていたはずの弟子たちは、群衆の前に出ていって、人々に福音を伝えたのです。
まず留まりなさい。しかし、聖霊が臨んだ時、彼らは爆発するように出ていきました。石さえも黙っていることができない状況になったのです。神である主が宣教の御業をなさる時のお決まりの流れです。私たちも毎聖日ごとに、これを経験していきたいと思います。
聖書をお開きください。エレミヤ書22:13-17(1330ページ)【聖書朗読】
「他の人とどのような関係をもって人生を歩むのか」というテーマで、御言葉から教えられてきました。私たちはそれぞれの人生の中で、他の人との関係に一番悩まされます。あらゆる実際問題の根源は、深く掘り下げてみると、人間関係に行き着くのではないでしょうか。
現代の人々は、人間関係の問題を色々と考察しています。人々は言うのです。「自分なりの答えを探してみよう。」しかし、それは賢いことではないと聖書は言っています。《知恵は、これを握りしめる者にはいのちの木。これをつかんでいる者は幸いである。【主】は知恵をもって地の基を定め、英知をもって天を堅く立てられた。(箴3:18-19)》と箴言に書いてあります。知恵とは神である主だけがご存知であり、私たちが自分の思考によっていくら考え抜いても分からない事柄のことです。主が私たちに明らかにしてくださった時にだけ分かる事柄を「知恵」と言います。主が御言葉から歴史を教えてくださらなければ、私たちは多くのことを知りませんでした。始めに人間はどのようにして造られたのか。夫婦は始め何を一緒にするようにと定められたのか。親子はなぜ造られたのか。家族はどんな様子で一緒に暮らすように意図されていたのか。隣人との関係はどうであるべきだったのか。そのようなあるべき姿を知ることはできなかったでしょう。また神である主を離れて、どの部分が、どのように壊れて、現在私たちを悩ませ、苦しめているのか、知ることはできなかったのです。今日は、義と公正を誠実に行うという観点から、町に起こっていることを学びたいと思います。
義と公正(ツェダカーtsed-aw-kaw'とミシュパーmish-pawt')とは何でしょうか。これはすでに聖書から学んできました。「神を愛し、隣人を自分自身のように愛すること」があらゆるところで行われるように教え、苦しめられている人を救い、暴虐を働く者たちを罰することです。具体的な教えが律法に沢山含まれていて、それらをひとつずつ見てきました。義と公正によって、すべての人は神様の前に等しく尊い存在として扱われ、愛による関係で結び合わされていくのです。しかし、この世は同じ「正義と公正」という言葉を使いながら、その意味を曲げてしまいました。人々の会話の中で「正義と公正」と聞くと、何となく争いの影を感じませんか。本来、権力ある人たちによって、正義と公正が行われるならば、それは普通の人たちにとって喜べること、味わうことができる尊いものであるはずです。ところが《彼らは、公正を苦よもぎに変え、正義を地に投げ捨てている。(アモス5:7)》と主が言われたことをアモス書は伝えています。美味しくて、人々を喜ばせるはずのものが、苦くなり、人々を苦しめるものに変えられてしまったのです。
「正義」神から離れた人々は、正義から愛を引き剥がしてしまいました。それは愛とは関係のないものになりました。アリストテレスやプラトンなど哲学者が正義を定義していきました。定規で測り、目盛りに足りるか不足するか、正義をそのようなものにしてしまいました。例えば、配分におけるその人の価値にふさわしい分けまえを意味するとか、罰によって不当な利益に損失を与えバランスを取るとか、そのような話に変わってしまったのです。
そのような世界の中で、神の民は律法を与えられて、義と公正に生きる人々として主を証しするはずでした。ところが彼らは主を裏切って、他の神々に従っていったのです。他の神々に従ったとは、異教の宗教的な儀式を熱心にするようになったという意味ではなく、他の国の人たちと同じように物事を考え、他の国の人たちと同じような生き方をしたという意味です。エレミヤ書の最初の方を読んでみると、主がそれを嘆いて悲しみ、怒っておられることが分かります。当時の民は、《『平安だ、平安だ(平和だ、平和だ)』(エレ6:14)》と言っていました。もし、あらゆるところで犯罪行為が行われていたのなら、人々が「平和だ、平和だ」とは言わないはずです。私たちは神である主が怒るぐらいだから、「不正によって豪華な家が建てられていた」とは、違法行為や暴力によって奪われ、人々があからさまに痛めつけられ、悪の組織が闊歩しているみたいな様子を思い浮かべるのではないでしょうか。隠れたところで違法行為があったとは思います。しかし、実際は私たちが今日、普通の世の中で見るのと同じような光景が広がっていたことでしょう。
アモス書8章を思い出してください。《聞け。貧しい者たちを踏みつけ、地で苦しむ者たちを消し去ろうとする者よ。あなたがたは言っている。「新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが。安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが。(8:4-5)》彼らは違法行為はしていません。安息日にしもべを休ませなければならないという法律を守っています。しかし、貧しい人を酷使してはいけないということを全然分かっていないのです。「法律は守っているだろ。安息日には仕事を休ませているだろ。安息日なんて早く終わらないかなと思っているだけじゃないか。いったい何が悪いんだ。」神の恵みを一緒に分かち合って、共に主の御前で喜び楽しもうという心はどこにあるのでしょうか。災害や災難、病気などによって貧しくなってしまった人たちを助けようという心はどこにあるのでしょうか。その人たちを、家族として見る心はどこにあるのでしょうか。すなわち、義と公正はどこにあるのでしょうか。主の民は義と公正に生きなければなりません。神を愛し、隣人を自分自身のように愛するように生きなければなりません。なぜなら、まず救い主である主が、民を義と公正によって贖い出してくださったからです。主の民は、まず主が彼らにしてくださったように、主に倣って生きるように召されたのです。そのように生きようとせず、他の国の人たちと同じように考え、同じように生きようとするなら、主は「あなたはわたしを裏切った」と言われます。
私はこのことを思い巡らす時に、ある事件を思い出します。「みんなが一生懸命お金を儲けて、法律のルールを破らなければって、ルールの中でお金を儲けちゃ何で悪いんですか」と言い放った人のことを思い出します。ルールを守れば利己的に生きても良い。これがこの世界がもっている罪の価値観なのです。主を恐れることを知らない生き方です。
神の義と公正に生きる人というと誰を思い浮かべますか。私はイエス様を思い出します。安息日に病を癒やし、人々にパンを与え、嵐を鎮め、悪霊を追い出されました。一方で、金銭を好むパリサイ人がいました。律法に精通しているはずのパリサイ人が金銭を好むとはどういうことでしょうか。抜け目なく自分の利益のために法律を利用しているのです。富める青年がいました。「先生、私は少年の頃から、律法を守ってきました」自分の正しさを示そうとして律法を持ち出しました。宮に来て、心の中でこんな祈りをしたパリサイ人がいました。「神よ。私がこの取税人のようでないことを感謝します。」他の人を見下すために律法を持ち出しました。彼らはみんな自分は正義と公正を行っていると勘違いしていました。バビロンを通して滅ぼされてしまった先祖たちと何一つ変わりませんでした。
私たちはどうでしょうか。やはり義と公正という言葉を誤解していることはないでしょうか。教会でも「正しさ」を巡って争いが起こります。世の価値観に従って「正しさ」を考えてしまうからです。神の愛と恵みに生きることが、主の目に正しいのです。箴言10、11章に正しい人が出てきますが、正しさに愛と恵みを関連付けて読んでみてください。主は愛と恵みの人を飢えさせず、悪しき者の欲を突き放される。愛と恵みの人の口はいのちの泉。愛と恵みの人の唇は多くの人を養う。町は愛と恵みの人の繁栄に小躍りする。愛と恵みの人の願いは、ただ良いこと。悪しき者の望みは激しい怒り。_みなさまもそれぞれで読んでみてください。
さて、ここで話を終えてしまうと、落ち込んでしまいそうです。いつものキーワードを思い出しましょう。「それにも関わらず」です。聖書の福音は「~だから」ではなく、「~にも関わらず」にあります。これを忘れないでください。
それにも関わらず、主はご自分の民に何とおっしゃるのでしょうか。同じエレミヤ書の4章で、主はこう言われました。《「イスラエルよ、もし帰るのなら、──【主】のことば──わたしのもとに帰れ。もし、あなたが忌まわしいものをわたしの前から取り除き、迷い出ないなら、また、あなたが真実と公正と義によって『【主】は生きておられる』と誓うなら、国々は主によって互いに祝福し合い、互いに主を誇りとする。」(エレ4:1-2)》主はわたしのもとに帰れと言われます。どんなことがあっても、あなたはわたしの愛する者ではないか。わたしのもとに帰れと。
ここにもイエス様が言われたの(ヨハネ13:34)と同じことが語られています。真実と公正と義によって『【主】は生きておられる』と誓うなら。すなわち主に誠実に従って、神の愛と恵みに生き、主を証しするなら、祝福が広がり、主の御名はあがめられるのです。これが神の宣教の計画です。主イエス様の愛と恵みを携えて、今週も出かけていきましょう。
お祈りします《あなたの父は食べたり飲んだりし、公正と義を行ったではないか。そのとき、彼は幸福であった。虐げられた人、貧しい人の訴えを擁護し、彼は、そのとき幸福であった。それが、わたしを知っていることではないのか。──【主】のことば──》
天の父なる神様。私たちの救い主になられた神。ご自分の民が苦しむときには、いつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが民を救いました。その愛とあわれみによって、主は民を贖い、昔からずっと彼らを背負い、担ってくださいました。
あなたは私たちを愛とあわれみによって救い出してくださいました。あなたは十字架によって、私たちの病を代わりに負ってくださったのです。あなたのような神は他にいません。
私たちはあなたに贖われ、あなたの弟子として、新しい歩みを始めました。御言葉を与え、足元を照らし、愛と恵みの生き方を教えてくださったのです。ところが、私たちは何と頑なで不従順な者たちでしょうか。初代教会の頃から今に至るまで、教会はあなたのみこころ行うことに度々失敗してきたのです。
主よ、どうか私たちをあわれんでください。世で習ってきた生き方ではなく、御言葉に示された神の知恵に従って、すなわち愛と恵みに生きることができるように助け導いてください。あなたのみこころを行うことを教えてください。
主イエス様のみ名によってお祈りいたします。アーメン。
![インマヌエル王寺キリスト教会[奈良県王寺町の教会]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpLQYEAtJ_uTBAe-KrJXjYYCIGsg0DZZgLlXZEed8SwMD5EoutkbLV7HQnNAPHceSLxKdJhO6npwzgl7R__tXPEKeiOd-oCmoPOkBKP0sjug9TR1UjhuomyCicvUQFdKiACuFVmb1q8sE/s1600/%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AB.png)



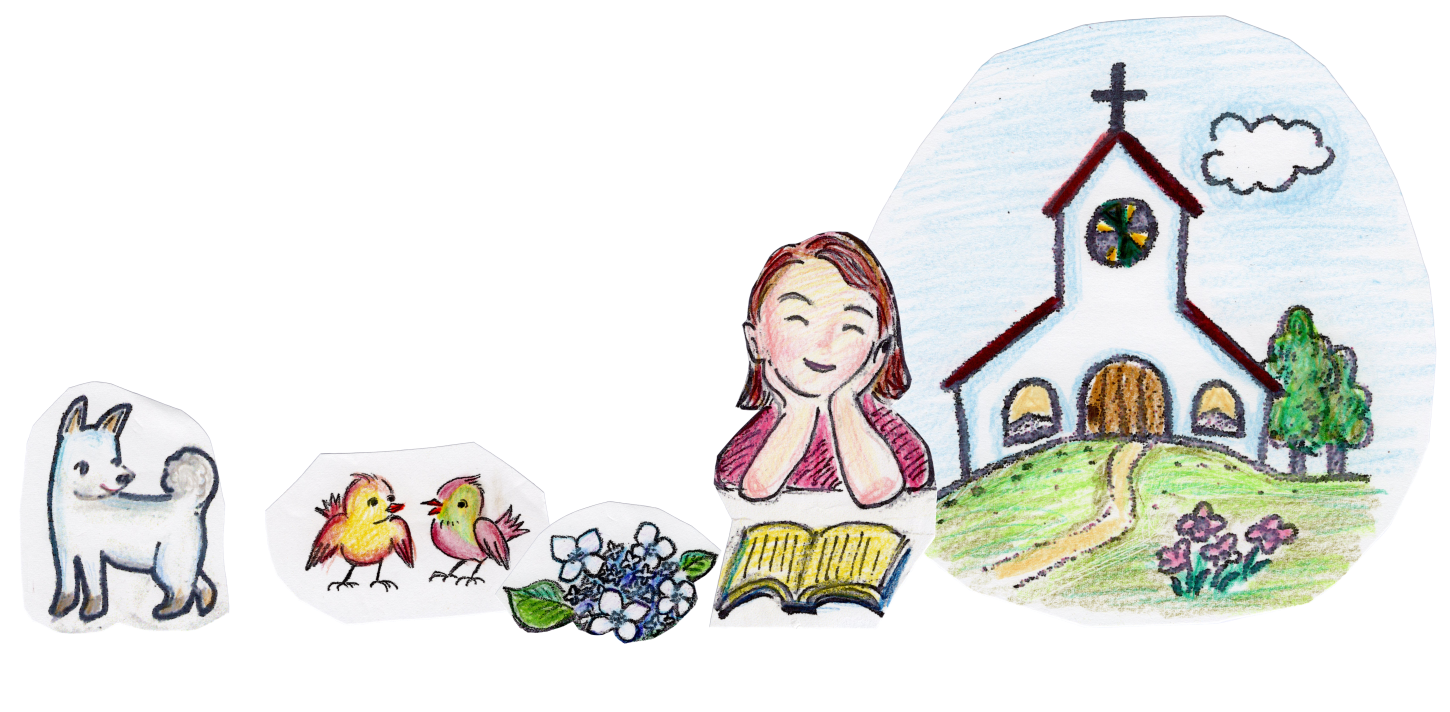
0 件のコメント:
コメントを投稿